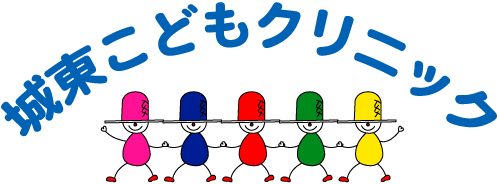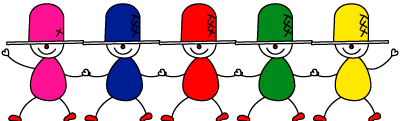日本小児科学会の今月号にビタミンD欠乏の予防の提言が載っていました。当院では以前から生後2か月で初めての予防接種に受診された赤ちゃんに、ビタミンDのサプリメントを紹介してきました。そこで、今日のブログはビタミンDがテーマです。
最近、生活・食事習慣の変化により、ビタミンDが不足する乳児が増加しています。ビタミンDは骨の発育に大切なビタミンです。欠乏すると低カルシウム血症から痙攣を起こしたり、くる病の原因となります。近年、ビタミンDはカルシウム代謝だけでなく、免疫や癌の予防、老化防止など体の様々な健康維持に関わる重要なビタミンであることが分かってきました。
乳児で必要なビタミンDの必要量は一日に0.005mgと言われています。母乳中にはビタミンDはほとんど含まれていません。食物では鮭や卵黄に多く含まれます。鮭15gで0.005mg、卵黄1個で0.0025mgのビタミンDが含まれているそうです。野菜とかお肉にはほとんど含まれていないので、乳児が食物だけから一日の必要量を取り続けることは困難です。
(※マイクログラムが表示されず、0.005mgと書きました。5マイクログラムです )
しかしビタミンDはお日様の光を浴びて自分の皮膚でも作られます。ですので、極端な日焼け止めの使用もビタミンD欠乏の原因となるのです。北国の冬、特に日本海側では日の差すことも少なく、また寒くて赤ちゃんを外へ出すこともなく、ビタミンDは容易に欠乏します。ガラスを通しての紫外線ではビタミンDは作られません。そんな理由から当院では天然型ビタミンDのサプリメントを勧めていたのです。
以下に小児科学会の提言を紹介します。
- 1.胎児のビタミンD欠乏を予防するために、妊婦だけでなく、将来を見据え小児期・青年期からのビタミンDを充足させるような生活・食事習慣を確立する。
- 2.母乳のビタミンD含有量は少ないが、ビタミンD補充の目的で母乳栄養が妨げられないようにする。
- 3.適度の外気浴、外遊びを行い、紫外線防止のため過度の日焼け止めの使用を行わない。
- 4.補完食(離乳食)の開始を遅らせない。
- 5.ビタミンDだけでなく、カルシウムの適正な摂取を行う。
- 6.ビタミンD欠乏のリスク要因となる生活環境・食事環境の改善が困難な場合には、天然型ビタミンDの乳児用サプリメントの使用を考慮する。
写真は我が家の愛犬です。犬もビタミンDは必要なんだろうか???
毛に覆われていて皮膚では作られそうにありません (^_^;)