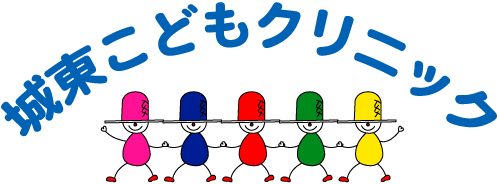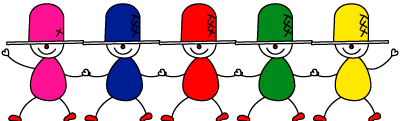NHKの自然科学番組は良質で優れているものが多いように思います。資金に余裕があるからでしょう。最近の「シリーズ人体」もその一つです。タモリさんと山中伸弥先生が出ているあの番組です。
NHKの自然科学番組は良質で優れているものが多いように思います。資金に余裕があるからでしょう。最近の「シリーズ人体」もその一つです。タモリさんと山中伸弥先生が出ているあの番組です。
たとえ医学分野であっても、最新の知見に基づいた自然科学番組で、自分の知らない話題がどんどん出て来ます。
先日放送された「命とはなにか」もそうでした。
細胞の話しで、細胞は、核やミトコンドリア、核小体などよく知られている構造だけではなく、それ以外の部分も様々な微細構造物や物質で埋め尽くせられており、それらの働き、ネットワークが次第に明らかになっているそうです。
番組ではその構造物の中でも、特に「キネシン」を取り上げていました。このキネシンは細胞の中で様々な物質を運ぶモーターたんぱく質で、微小管とよばれるレールの上を、2本足でまるで歩くように運ぶのだそうです。(実際に電子顕微鏡でも、その2本の足が写っている!)その荷物を運ぶ様子をCGの映像で見せてくれていました。ちょっとやり過ぎの感はありますが、それでもリアルに思えて、理解を助けてくれます。
さて、自分がとても興味深く思ったのは、そのキネシンの量が環境によって変わるというのです。玩具や仲間に囲まれたマウスと、仲間の少ない殺風景な環境に置かれたマウスではキネシンの量が少なくなることが実験で明らかになったのです。すなわち、環境が細胞レベルにまで影響を与えるのです!!
詳しくは書きませんが、神経細胞の働きにまで影響し、感情さえも左右する。日常の臨床で何となく理解してきたことが、細胞レベルで証明されたように思えました。
 エピジェネティクスという言葉があります。
エピジェネティクスという言葉があります。
色んな病気に遺伝子が深く関わっていますが、同じ遺伝子を持っていてもそれが病気として発症することもあれば、発症しないこともある。そこには遺伝子以外の因子が関わっています。生活環境であったり、社会環境であったり。若しかしてそのメカニズムも細胞レベルの話しなのだろうと想像していました。
写真上は湯段のミズバショウ沼公園、写真下は百沢の桜林です。