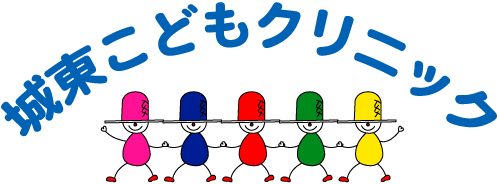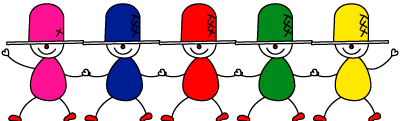10月1日から青森県の主導で小児のオンライン診療が始まります。土日祝祭日も含めて1年365日、毎日午前6時から午後8時までの14時間、診療を受けることが出来るそうです.受診希望の人はスマホでアクセスし、15分以内の待ち時間で診察を受けることが出来るそうで、診察する医師は東京のFastDOCTORという組織の医師だとか。
宮下知事のアイデアで、自治体主導で県単位で始めるのは全国で初めてだと聞きました。受診することのできる対象は県内に住む小児。但し、全身状態が悪い子どもは除外されるそうです。知事はこれで、都市部でも無医村の地域でも、予約無し、待ち時間無しで診療を受けることが出来るとしています。
県の小児科医会は反対意見を出しましたが、大した議論が交わされることもなく、一方的に開始することが決まってしまいました。公聴会も開かれたようですが、実施することは初めから決まっていたようだったと聞きました。
さて、それが良いことなのか悪いことなのか。
何故、小児科医会は反対したのか。
確かに様々な事情で診察を受けれられない子にとっては福音かも知れません。小児科医のいない地域に住んでいるとか、予約が取れないとか、待ち時間が長すぎるとか。しかし様々なデメリットもあります。その一つは、果たしてビデオを観ただけで正確な診断が出来るのかということ。親御さんの訴えだけで病状を正確に把握することは困難です。軽症に見えても実は重症だったと言うこともままあります。また、小児科医はただ単に病気だけを診ているわけではありません。その子の発育や発達、予防接種歴、家族背景など多角的に子どもを観ています。
もう一つの気懸かりは誰が診察するかです。どうも診察医は小児科医でないこともあるようです。先の団体に登録してある医師の数は4000名と聞きました。しかしその中で小児科の専門医となると数名しかいないそうです。
たとえ小児科専門医であったとしても、お話を聞くだけで正確な診断は下せません。例えば咽頭炎の溶連菌感染症を問診だけでは診断できません。実際に喉を観て、皮疹がないか確認し、リンパ節の腫脹がないか触診する必要があります。少なくとも自分は怖くてオンライン診療をやる気にはなれません。
オンライン診療という簡便な診療行為が広まることで、一般の開業小児科医院、あるいは病院小児科の経営を圧迫しないかということも懸念されています。ただでさえ、小児人口の減少で小児科医院の経営は難しくなり、新規に開業する小児科医はとても少なくなりました。青森市も弘前市も小児科医院はどんどん減ってきています。もし我々がいなくなると地域の小児医療はどうなってしまうのだろうという心配があります。
この開業小児科医の減少はかなり心配なことで、オンライン診療があろうがなかろうが、確実に減ってきています。弘前でももう10年もしないうちに2,3件は閉院すると予想されます。その時、今と同じ小児診療態勢を維持することは不可能かも知れません。子ども達を誰が診るか、小児の救急医療態勢は維持できるのか、予防接種や乳幼児健診は?、今のうちから対策を考える必要があるでしょう。

写真は丸亀城。外来小児科学会で高松を訪れた際、隣町まで足を伸ばしました。天守閣は小さかったですが、石垣が見事でした。あんなに高い石垣なら大きな天守閣を作る必要はないなと理解しました。
そうそう、お堀を泳いでいたのは鯉ではなく、亀でした (^o^)